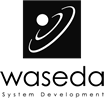2021.05.26
「特需」を取るべきか、「持続可能性」を重視するべきか
#私的考察
もう十数年も前になるのですね。かつて、大手銀行が「ビジネスローン」という中小企業向けのパッケージ融資を競うようにプッシュしていた時代をご記憶でしょうか。
メガバンク3行で数兆円規模の融資合戦(?)は、もちろん中小企業支援の強化が目的でした。それ以前に社会問題化していた「貸し渋り」「貸し剥がし」の時代と同一機関とは思えないほど審査が簡易化される中、数百万円から数千万円のつなぎ資金を簡単に借りられる。バブル経済の崩壊以降、延々と長引く不況に喘いできた中小企業の経営者の目には、まるで天から垂れる蜘蛛の糸のように見えたに違いありません。
ところが、2年ほど経って、そんな彼らが耳を疑うようなニュースが舞い込みます。何と、このわずかな期間で、政府が方針を転換したというのです。それまでバルブを全開にしたような状態だった銀行各行は、当然のことながら開閉スイッチに指を伸ばし、ビジネスローンの折り返し資金の融資を渋らざるを得なくなります。そうなると、下手に借りてしまった分、返済のために資金繰りが悪化する企業も。中には、倒産につながった例もあったそうです。
これはあくまで一般企業の話ですが、実は、ミュージアムにとっても他人ごとではありません。政府は、ある政策を推進したい時、そこに大規模な予算措置を講じます。補助金を付けてもらえるなら、それを機会に、ひとまわり規模の大きな事業の企画が生まれることもあります。首尾よく実施へと移行でき、大きな成果を得ることもあるでしょう。
それ自体は素晴らしいことで、お金を出す側にも使う側にも、まさに理想的な事業となり得ます。しかし、弊社でも、私個人でも、機会があるたびに常々申し上げているのは、「継続性」です。もしも後年に維持費の捻出を要する企画であれば、次年度からは補助金が付かないことも計算にいれておかなければなりません。と言うのも、地域社会的によほど注目を浴びた企画でもない限り、維持のための予算は確保しづらいのが一般的なのです。
手前みそながら、弊社のクラウド型システムは、まさにこの問題に直面する中で生まれたアイデアです。新規導入時は大型予算がついても数年後のリプレースの資金を用意できず、ハードウェアの老朽化とソフトウェアの陳腐化に苦しむ中小規模の博物館の姿を目の当たりにして、「無理なく継続できる方法はないか」という発想から企画したサービスでした。
最近は持続可能性という言葉が一般的になりましたが、検証の上で継続のための予算は確保できると確信できても、不意の事態に晒されることもあります。ひとつの例が、昨年来、近年の盛り上がりが一瞬でかき消されることになった国際観光政策、インバウンド事業です。世界的な日本ブームもあり、一時はあらゆるメディアで「観光立国」というキーワードが踊ったのは記憶にも新しいところ(いや、遠い昔のようでもありますね)。まさか世界中が新型ウイルス感染のパンデミックに襲われてフリーズするとは、誰もが夢にも思わなかったでしょう。
コロナ禍はレアケース中のレアケースですが、仮にこの事態がなかったとしても、実は「ポスト五輪」の時代に向けてインバウンド政策がどう進むかについては、少なからず議論がありました。訪日外国人数がうなぎ登りの時代が落ち着いたら、それ以降はどうなるのか、どうするのか。私は、この話題にふれるたびに、「前回の日本の五輪」を思い出しましたものです。
それは、東京五輪ではなく、長野冬期五輪のこと。当時、地元のタクシー会社は、次々と押し寄せる報道関係者の貸切予約という「特需」で沸いていました。規模は違いますが、少し前の日本のインバウンドブームに似ていますね。
そんな中、あるタクシー会社の運転手たちが連れ立って社長室に向かい、「彼らの団体の貸切予約を断ってほしい」と直談判したそうです。理由は、驚くほどシンプルでした。曰く、いつも自分たちの車を利用してくれるお年寄りが困るから。現場からの要請を受けた社長は、団体予約をすべて断ることにしました。誠に素晴らしい決断ですが、中小企業の経営者としては、せっかく目の前にお客さんが列を成しているのに…と断腸の思いもあったのではないでしょうか。
ところが、この経営判断は、この会社に有利な方向へと作用します。なにしろ、冬季五輪の開催期間中はその会社でしか配車してもらえないわけですから、他社の常連客も一時利用することになります。車が空いていた理由を聞き、発案者である運転手たちの温かみに触れた人々は、五輪が終わっても利用を続けました。結果、そのタクシー会社は、県内ナンバーワンの存在になったそうです。
特需を見逃さないことは、事業の成長性をつかむことに直結します。しかし、持続可能性を見失うと、不意の環境変化が脅威となります。重要なのは、きっと、バランス。長野のタクシー会社の物語は、企業経営者の間では割と有名なエピソードであり、教訓です。