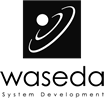2025.04.09
たった1枚のWebページを追加しただけで魅力倍増、 住民参加型デジタルアーカイブ ~パルテノン多摩ミュージアム地域資源データベース
提供機関 | パルテノン多摩ミュージアム
URL | https://www.parthenon.or.jp/museum-database/top
構築方式 | オリジナルサイト・リンク
実は、作ったのはWebページわずか1枚だけ!

パルテノン多摩ミュージアムのホームページからアクセスできる「地域資源データベース」は、まず名称からして「収蔵品」「所蔵の品」ではなく「地域資源」と名付けている点が象徴的。ここで閲覧できるデータは地域住民の資源、資産であるという宣言に他ならず、館の姿勢がはっきりと伝わるタイトルと言えるでしょう。同時に、トップに用意された大きな3つのボタンも、それぞれに何を閲覧できるのかがひと目で分かる仕様に。いずれも閲覧者の目には「自分ごと」と映る設計となっており、タイトルとボタンだけで思わず引き込まれそうになります。
これらのボタンのリンク先で公開されている地域資源は、多摩ニュータウン開発前の写真や航空垂直写真・斜め写真、民俗資料や植物、パブリックアートまで多岐にわたります。一般の方々が探したい資料に自力で辿り着くのは困難と思われますので、まずは「地図」「年代」「ストーリー」という3つの軸に絞ったのは、「助かります!」という声が聞こえてきそうなシンプルさです。

それぞれのボタンをクリックすると、同じページの下にある各コーナーにジャンプします。地図からの検索では各エリアの地域資源の一覧画面を閲覧できますが、地図上に書かれた地域名のほか一覧表示された地域名をクリックしても開きます。地図を見て少し驚くのは多摩市内だけに留まらない点。パルテノン多摩ミュージアムは東京都多摩市に所在するミュージアムなのですが、もっと広義的に「多摩ニュータウンの昔の姿」を見たい人にとっては行政基準の線引きは確かに無用。ここでも利用者目線の設計が光ります。
さて、ミュージアムとしての大きな特徴のひとつが「市民学芸員」の存在です。他の自治体でも取り組み事例の多い利用者参加型のプロジェクトですが、こちらでは何と市民学芸員の皆さんの活動成果も登録・公開されているのです。

「ストーリーから地域資源を見る」をクリックしてコーナーに移動すると、大きな写真が並んでいます。インスタントカメラ風の写真は、これもデータベースへの入り口にあたるボタンの役割を果たしています。たとえばここで「街角アート(彫刻)」を選ぶと、屋外に設置されたパブリックアートの写真が一覧表示されます。

実は、これらの写真の多くが市民学芸員の方々の活動成果。パブリックアートを調査の上でリスト化し、画像ファイルとともにミュージアムに提出すると、館の学芸員のチェックを経てシステムに登録され、デジタルアーカイブで公開されるという仕組みで運営されているのです。

それぞれの詳細ページには、写真のほか解説もしっかり掲載されていますね。写真撮影や詳しい調査内容の報告で市民学芸員の仕事は無事に完了…ではなく、これら成果をもとに館内展示や鑑賞ツアーを実施した実績もあるそうです。また、このコーナーには5つのテーマが用意されていますが、ほかにも多様な切り口が設定されており、市民学芸員の活動は今も活発に進行中とのこと。活動成果が公開されることがモチベーションのひとつとなり、公開される地域資源情報が継続的に増えていく…という好循環が仕組み化されているわけです。
シンプルながら分かりやすい画面のこのデジタルアーカイブも、I.B.MUSEUM SaaSの搭載機能だけで構築されています。しかも制作したのは、実は1ページ分のWebページだけ。大掛かりなシステムでなくても、別に予算を捻出しなくても、利用者目線&市民参加型のデジタルアーカイブの構築は十分に可能と教えてくれる注目事例です。